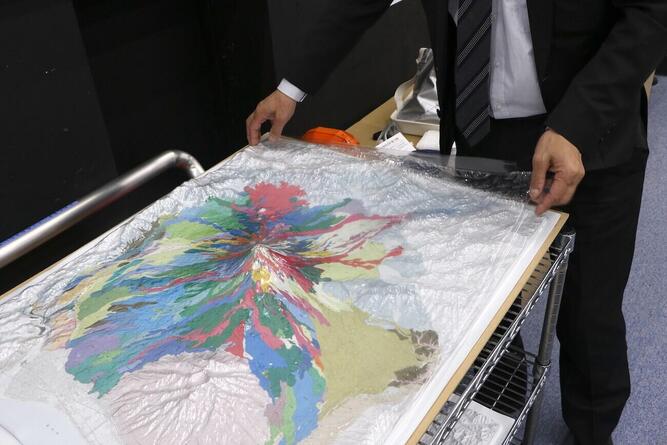ヒバカリとは?日本在来の小さくてかわいいヘビ
※ヘビの画像が出てきます。苦手な方は閲覧にご注意ください。
ヒバカリというヘビをご存じですか?
ミミズみたいに小さな日本在来種のヘビです。自然環境の変化や開発で全国的には希少な生物となりましたが、ここ山梨では比較的生息数は多いようです。
ヒバカリとは?分布と生態
ヒバカリ(学名、Hebius vibakari)は本州、四国、九州に分布し、水田や河川沿い、里山、森林など広い範囲に生息します。市街地ではあまり見かけませんが、水田が多い地域なら見かけることがあるでしょう。
小さくつぼめたようなおちょぼ口でかわいいです。もちろんヘビが苦手な人はそう思えないでしょうが。
ヒバカリは日本で一番小さなヘビの一つで、体重はわずか10~25gほど。
夜行性で、夕方から夜にかけて活動し、昼は石の下にいることが多いです。小さなカエルやオタマジャクシ、ミミズ、ドジョウなどを食べます。
刺激すると匂いのある体液を出すことがありますが、毒はありません。
体は幼蛇では体は褐色、成蛇では薄い褐色(黄褐色)や赤みを帯びたりします。幼蛇では首の後ろにかけて襟のような白い模様が斜めに入ります。お腹は淡いクリーム色で,幼蛇は背中の褐色との間に紅梅色の部分があります。
ヒバカリは自治体レベルで絶滅危惧種
ヒバカリは環境省のレッドデータブックには記載されていませんが、自治体レベルでは複数の都道府県で絶滅危惧種に登録されています。
たとえば、東京都と大阪府では「絶滅危惧Ⅱ類」、また千葉県、神奈川県、埼玉県では「準絶滅危惧種」に指定されています。
個体数が減少した理由は、水田などの生息環境が減少し、特に都市部で、住処がなくなったり、ヒバカリにとっての餌が得にくくなったためです。
このように特定の環境でしか生きられず、環境が少し変化しただけで個体数など敏感に反応する生物を「指標生物」と言い、自治体の環境調査や開発時の環境アセスメントで調査対象となります。
たとえば、横浜市では、ヒバカリは耕作地生態系の「目標生物指標種」とされ、ヒバカリがいれば理想的な自然環境であると解釈することになっています。
ヒバカリの名前の由来は「噛まれたら命はその日ばかり」
ヒバカリはかつて毒蛇と考えられていて、「噛まれたらその日ばかりの命」という意味で、ヒバカリと名前が付いたそうです。
実際には、ヒバカリは無毒とされています。ただし、同じく長年「無毒」と考えられていたヤマカガシが、実は後牙に毒を持っていたこともあったので、ヒバカリにいくら噛まれてもいいということではないでしょう。
ヒバカリはペットとしても人気
ヒバカリは爬虫類愛好家の間で人気があり、ペットとして飼われることもあります。
成長しても40cm程度と手に乗るサイズでかわいらしく、それでいて寿命は10年と長いのが特徴です。比較的おとなしい性格とも言われます。
ただし、基本的にはミミズやカエルなどの生き餌が必要となります。カメの餌などで餌付けできる場合もあるようですが、必ずしもうまくいくとは限らず、飼育が簡単なペットではありません。
以上、日本の小さなヘビ「ヒバカリ」についてでした。
written by ヒノキブンコ