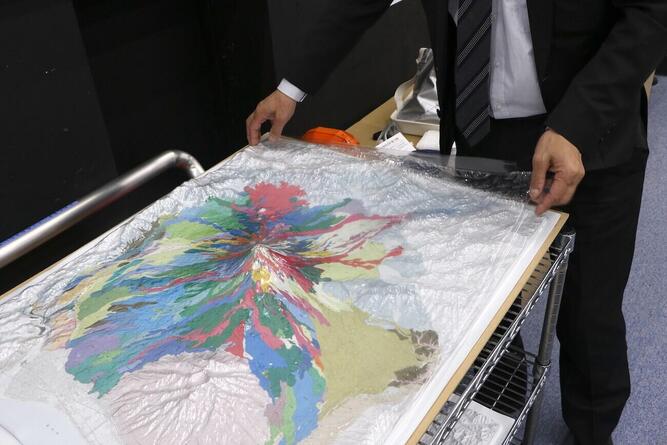タヌキとは?その生態や被害の対策について
タヌキ(狸)は日本で身近なイヌ科の野生動物です。
- 目 次
- 1. タヌキとは?分布と生態
- 2. タヌキの赤ちゃんはイヌに似ているその理由は?
- 3. 日本のタヌキは固有種の可能性がある
- 4. タヌキに似ている動物との見分け方
- 5. タヌキの被害と対策
- 6. タヌキにまつわる慣用句・ことわざ
タヌキとは?分布と生態
タヌキは北海道、本州、四国、九州に分布し、市街地や河川沿い、里山、森林など広い範囲に生息します。
トウモロコシ、イモ、マメ、果実、植物の葉や芽、昆虫、カニ、魚、動物の死骸などを食べる雑食性。餌を求めて5km移動することも。夜行性なので暗くなってから活発に活動を始めますが、昼間も活動することも多いようです。
タヌキの赤ちゃんはイヌに似ている!その理由は?
タヌキはイヌやオオカミと同じイヌ科のグループです。そのため、タヌキの赤ちゃんは犬の赤ちゃんと似ています。子犬と間違えられて拾われて飼われることもあるそうです。
日本のタヌキは固有種の可能性がある
タヌキは朝鮮半島、中国、ヨーロッパなど大陸に広く分布しますが、最近日本列島のタヌキは大陸種とは異なる日本在来の固有種であるという研究が出てきました。
これは遺伝子解析や頭骨の分析によるもので、現在日本の研究者により日本のタヌキの学名変更が提案されています。
アナグマも同じケースと言えます。日本だけでなく中国やヨーロッパなど大陸に分布し、これまで同種(1種)とされてきました。しかし、遺伝子解析等により日本系は別種と位置づけられることが分かり、「ニホンアナグマ」と改名されて日本固有種になりました。
タヌキに似ている動物との見分け方
タヌキと似た動物に、アライグマ、ハクビシン、アナグマがいます。
アライグマはアライグマ科、ハクビシンはジャコウネコ科、アナグマはイタチ科と、姿は似ていても、実はみな別のグループということになります。
下図に違いをまとめました。
タヌキはアライグマと似ていますが、耳のふちが黒ければタヌキ、耳のふちが白ければアライグマです。
タヌキはハクビシンにも似ていますが、ハクビシンは耳が丸くて黒く、尻尾も長いので区別できます。
タヌキの被害と対策
タヌキは雑食性ゆえ、ぶどうやサツマイモ、柿、スイカ、トウモロコシなどの農作物に被害を与えます。
また、タヌキは複数の個体が同じ場所に糞をする「ため糞」という習性があり、これが農地や家の敷地内にできてしまうと、悪臭や衛生問題につながります。
タヌキを畑や家の周りに寄せ付けないためには、畑の野菜や果実を残さない、庭に生ごみを置いたり、畑に埋めたりしない、ペットフードを出しっぱなしにしない、などタヌキの餌となるものをなくすことがポイントです。
農地への侵入を防ぐには、垂直に登るのが苦手なタヌキの習性を利用して、策を設けたり、被害が大きい場合は捕獲器で捕獲するなどの対策が有効となります。タヌキは鳥獣保護法の対象なので、許可なく捕獲することはできません。自治体に申請して許可を得た上で捕獲します。
タヌキが家の屋根裏や床下に住み着くことも少なくありません。そうなると、騒音やダニの被害などを引き起こすことがあります。
そんなときは、まずは侵入経路をふさぎ、忌避剤などで追い出すのが有効。ホームセンターにも、タヌキの忌避剤、匂いシート(ミント、ハッカ、トウガラシなど)が売っています。妊婦や小さなお子様がいる家庭で使って大丈夫かなど、商品の説明に従って使用します。
タヌキにまつわる慣用句・ことわざ
タヌキは昔から私たちの生活に身近な動物だったので、慣用句やことわざにも登場します。
「たぬき寝入り」・・・寝たふりをする。タヌキは驚くと「擬死」状態になる習性から
「取らぬたぬきの皮算用」・・・手に入るかどうか分からないものを当てにして計画を立てること。確定していない利益を見込むこと
以上、『タヌキとは?その生態や被害の対策について』でした。
共同トイレでちゃんと用を足し、寒い時期にはもふもふ姿になるタヌキが、なんだかかわいらしく見えてきました!
written by ヒノキブンコ