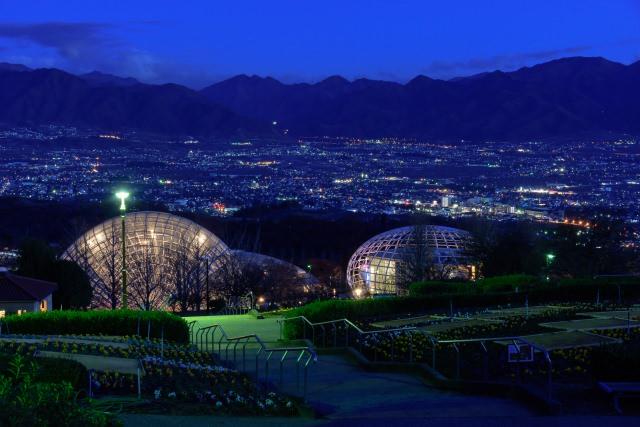「甲斐善光寺」武田信玄によって創建された甲斐の名刹
信玄公が川中島の合戦の折に信濃善光寺の焼失を恐れて、建立したことがはじまり

JR酒折駅から歩いて約15分、甲府市善光寺という住所にもなってる「甲斐善光寺」は、永禄元年(1558)武田信玄公が川中島の戦いで長野にある信濃善光寺が戦火に遭うのを恐れ、本尊の阿弥陀如来をはじめ諸仏や寺宝類を甲府に移したことが始まりです。

その際、僧侶やまちの人々も甲府に住居を移し信濃善光寺と同様、門前町として本堂の周囲には多くの宿坊が存在していたといいます。金堂と山門は国の重要文化財に指定され、撞木(しゅもく)造りの金堂は、東西約38メートル、南北約23メートル、高さ約26メートルを誇る、東日本最大級の木造建築物です。
一光三尊式善光寺如来像の中で最も古い御本尊
7年に1度のご開帳時には、30万人が訪れる

長野県にある信濃善光寺の御本尊は、古くから生命が宿る霊像として深く信じられており、東大寺二月堂のご本尊、雷門の浅草寺のご本尊とともに、絶対秘仏として現在までその顔を拝むことはできません。建久六年(1195)直接拝むことができる御本尊の前立仏を造立し、川中島の戦いの折には御本尊とともに「甲斐善光寺」に保護されました。武田氏の滅亡以後、秘仏である御本尊は天下人のステータスとして織田・徳川・豊臣氏を転々とし、慶長三年(1598)現在の信濃善光寺に戻りました。「甲斐善光寺」では、保護していた前立仏を新たに御本尊として祀り、大いなる信仰を集めてきました。一光三尊式善光寺如来像の中では在銘最古かつ例外的に大きな等身像(高さ147.2cm、重さ242kg)として存在し、7年に1度のご開帳時(次回は2027年4月~6月半ばまで予定)には、30万人が一目見たいと訪れます。
日本一の鳴き龍、お戒壇巡り

金堂中陣天井には、日本一の規模を持つ巨大な「鳴き龍」が描かれ、手を叩くと天井と床が共鳴し「ビーン」という音(多重反響現象)が響きます。現存する金堂は江戸時代中期に再建されたもので、再び災いが起きないよう水の使いである龍を描いたのではないかと言われています。

金堂の最奥に進むと、「お戒壇めぐり」の入口が現れます。「仏様の胎内巡り」とも言われ、御本尊の真下を通る一寸先も見えない暗闇の中を進み、途中の「極楽の錠前(じょうまえ)」に触れることで、御本尊と深い縁を結び、新しい自分に生まれ変わるという意味合いを持つ修行です。「心」という字でかたどられた回路は、すぐ目の前にあるものがまったく見えなくなる恐怖と普段は感じないことを体験できる、まさに心洗われる空間になっています。
宝物館には、日本最古の源頼朝像も
寺を訪れることで、過去に学び、親しみや心のよりどころに

「甲斐善光寺」の金堂の隣にある宝物館には、武田信玄公が信濃善光寺より移した宝物の一部を、随時展示替えを行いつつ年中無休で公開しています。その一つ、源頼朝像としては日本最古の彫像である「源頼朝木像」は、現在教科書や参考書等で「実像にもっとも近いもの」として広く紹介され、直接歴史と繋がることができる空間は、憧れの人に会えるような高揚感をもたらします。

武田信玄公が創建し450年以上、火災に見舞われながらも人々の信仰と大切なモノを守ってきた「甲斐善光寺」。73代目住職を支えながら、次の世代へ継承するための役割を担う副住職・吉原知仙さんは、「昔のことを学ぶことが、寺への親しみや信仰に繋がっていく」と話します。
「お寺を大切にし歴史を次の時代にきちんと継承していくことが、私たち寺の役目 です。「甲斐善光寺」では、いろんな歴史に触れていただく宝物などをできる限り開放していますが、過去に学び人々の心の拠り所に少しでもなればと願っています。」
2024年から金堂の調査が行われ2027年から6年間修復工事に入る「甲斐善光寺」。悠々と時が流れる名刹で歴史や信仰にじっくりと向き合い、静かに心を澄ませてみてはいかがでしょうか。
Article written by VALEM co., ltd.
甲斐善光寺
山梨県甲府市善光寺3丁目36−1
※詳細は下記URLを参照してください。
http://www.kai-zenkoji.or.jp